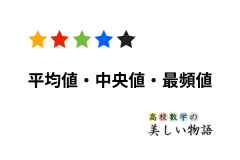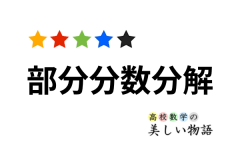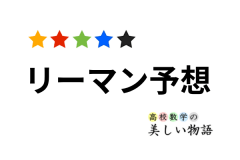漸化式 に関する12記事をまとめました。くわしくは各リンク先を見てください。
漸化式(ぜんかしき)についてわかりやすく解説します。漸化式の意味から,解き方12パターンをすべて紹介します。
→漸化式の解き方12パターンと応用例まとめ
確率漸化式の解き方の流れ
- 求めたい「n 回目の確率」を an とおく
- an と an−1 の関係を漸化式で表す
- 漸化式を解く
→確率漸化式の解き方と例題
an+1=pan+f(n) は d 回階差を取ることによって上記の「f(n) が定数の場合」に帰着できる
→f(n)を含む二項間漸化式の2通りの解法
攪乱順列(完全順列)の個数
n≧2 とする。1 から n までの整数を並び替えてできる順列のうち,すべての i について「i 番目が i でない」を満たすものの個数 an は
an=n!k=2∑nk!(−1)k
→攪乱順列(完全順列)の個数を求める公式
フィボナッチ数列
フィボナッチ数列(fibonacci sequence)とは,
- 最初の2つは 1 で,
- 3つめ以降は「前の2つを足したもの」
になる数列のこと。つまり,
1,1,2,3,5,8,13,21,34,…

→フィボナッチ数列の8つの性質(一般項・黄金比・互いに素)
母関数
数列 an に対して,
f(x)=k=0∑∞akxk
を(数列 an の)母関数と呼ぶことがある。
→数列の母関数の意味とその応用例
ウォリス積分
∫02πsinnxdx=∫02πcosnxdx=⎩⎨⎧n!!(n−1)!!n!!(n−1)!!2π(nが奇数)(nが偶数)
→ウォリス積分~sinのn乗,cosのn乗の積分公式
三項間漸化式の特性方程式の解を
α,β
とおくと,漸化式の一般項は
an=Aαn+Bβn
と表される。A,B
は初期条件から求める。
→三項間漸化式の3通りの解き方
方針
漸化式
an+1=4an(1−an)
は,a1=sin2θ
と置くと倍角公式が出現してうまくいきます。知らないと厳しい問題です。
→ロジスティック写像と漸化式
漸化式で表される数列の極限を求めるタイプの入試問題は頻出です。問題の背景にはバナッハの不動点定理と呼ばれる素敵な定理があります。
→漸化式で表される数列の極限
東京大学理系数学2025年 第5問
n を 2 以上の整数とする。1 から n までの数字が書かれた札が各1枚ずつ合計 n 枚あり,横一列におかれている。1 以上 (n−1) 以下の整数 i に対して,次の操作 (Ti) を考える。
(Ti):左から i 番目の札の数字が,左から (i+1) 番目の札の数字よりも大きければ,これら2枚の札の位置を入れかえる。そうでなければ,札の位置をかえない。
最初の状態において札の数字は左から A1,A2,⋯,An であったとする。この状態から (n−1) 回の操作 (T1),(T2),⋯,(Tn−1) を順に行った後,続けて (n−1) 回の操作 (Tn−1),⋯,(T2),(T1) を順に行ったところ,札の数字は左から 1,2,⋯,n と小さい順に並んだ。以下の問いに答えよ。
- A1 と A2 のうち少なくとも一方は 2 以下であることを示せ。
- 最初の状態としてありうる札の数字の並び方 A1,A2,⋯,An の総数を cn とする。n が 4 以上の整数であるとき,cn を cn−1 と cn−2 を用いて表せ。
→【解答・解説】東大理系数学2025 第5問
カタラン数
カタラン数とは,
cn=n+12nCn
で定義される数 cn のこと。
→カタラン数の意味と漸化式