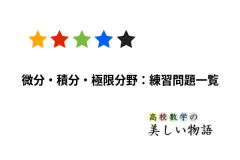ステップ1
まずは与えられた式を整理して見通しをよくします。
ステップ1
g(x) は連続関数であるため,h(x) は微分可能である。これより f(x) の微分可能性も従い,g(x) の微分可能性も従う。
まずは条件式を辺々 x で微分する。
f′(x)g′(x)h′(x)=−ah′(x)exp(−h(x))=−f(x)h′(x)=dxd(∫0x(f(y)−1)dy)×bexp(∫0x(f(y)−1)dy)=(f(x)−1)g(x)=g(x)
よって
⎩⎨⎧f′(x)=−f(x)h′(x)g′(x)=f(x)g(x)−g(x)h′(x)=g(x)⋯(∗)
を得る。
g(x) が最大値を取る場合,g′(x)=0 のみであるため,このような x の条件を求める。g′(x)=(f(x)−1)g(x) であるため,以下 f(x)=1 となる x を求める。
(∗) の辺々を足すと
f′(x)+g′(x)+h′(x)=−f(x)h(x)+f(x)g(x)−g(x)+g(x)=−f(x)g(x)+f(x)g(x)=0
であるため,f(x)+g(x)+h(x) は恒等関数である。
特に
f(x)+g(x)+h(x)=f(0)+g(0)+h(0)=a+b
である。
ステップ2
次に f(x)=1 の解が存在することを確認します。
ステップ2
また b>0 であることと,任意の実数 x について ex>0 であることを合わせると g(x)>0 を得る。
h′(x)=g(x)>0 より h(x) は実数全体で(狭義)単調増加であることが分かる。これと f(x) の定義から f(x) は単調減少であることが分かる。
f(0)=a>1 であるため,ある x0 で f(x0)≦1 であることを示せば,中間値の定理より f(x)=1 の解が存在する。また f(x) は単調減少関数であるため,解はただ1つ存在することが分かる。
任意の x で f(x)>1 であることを仮定する。
このとき,g′(x)=(f(x)−1)g(x)>0 であるため,g(x) は単調増加である。ゆえに g(x)≧g(0)=b である。このとき
h(x)=∫0xg(y)dy≧∫0xb dy=bx
より x→∞limh(x)=∞ となる。
f(x)+g(x)+h(x)=a+b であることと,g(x)≧>0 であることから x→∞limf(x)=−∞ となる。これは
f(x)=aexp(−h(x))>0
と反する。
以上より,ある x0 が存在し f(x0)=1 となることが分かる。また,このような x0 は1つしか存在しない。
ステップ3
ラストスパート,計算です。
ステップ3
以上の議論から g の増減表は
xg′(x)g(x)0b⋯+↗x00⋯−↘
である。ゆえに g(x) の最大値は g(x0) である。
f(x0)=1 である一方,
f(x)=aexp(−h(x))
に x=x0 を代入して対数を取ると
h(x0)=loga
が従う。
f(x)+g(x)+h(x)=a+b であったため,
h(x0)=a+b−f(x0)−h(x0)=a−loga+b−1
である。