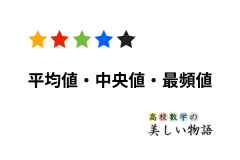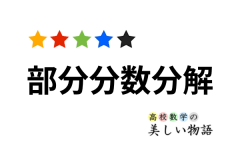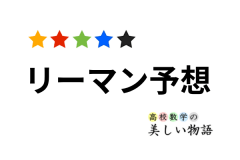dxd∫p(x)q(x)f(t)dt=f(q(x))q′(x)−f(p(x))p′(x)
例えば
dxd∫2xsinxetdt=esinxcosx−2e2x
という感じです。公式を覚えるというよりも導出方法を理解してください。
証明1(冒頭の公式の証明と同じノリ)
f(x)
の原始関数の1つを
F(x)
とおくと,公式の左辺は
F(q(x))−F(p(x))
となる。
これを
x
で微分すると(合成関数の微分公式より),
f(q(x))q′(x)−f(p(x))p′(x)
となる。
証明2(冒頭の公式を使う)
公式の左辺を変形していくと,
dxd(∫0q(x)f(t)dt−∫0p(x)f(t)dt)=dxdq(x)dq(x)d∫0q(x)f(t)dt−dxdp(x)dp(x)d∫0p(x)f(t)dt
ここで冒頭の公式を使うと,上式は
dxdqf(q(x))−dxdpf(p(x))=f(q(x))q′(x)−f(p(x))p′(x)
となる。
高校数学では積分方程式という言葉は登場しませんね。
Tag:数学3の教科書に載っている公式の解説一覧