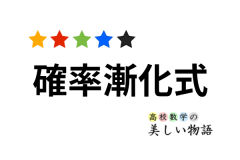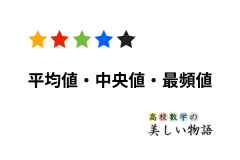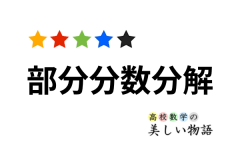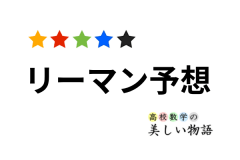ワイル代数
定義
微分と関数倍する操作を組み合わせることで,「関数から関数への関数」が定義できます。このような「関数」を微分演算子といいます。
微分演算子の集合のなかでも「x 倍する操作」と「x で微分する操作」から生成される集合をワイル代数といいます。今回の場合,コイントスの結果 ex を fN(x) に対応させる演算はワイル代数の元になっているのですね。そのため,ワイル代数の構造を活かして議論をしたいわけです。
さて,ワイル代数の一番重要な性質を紹介しましょう。
ワイル群の交換関係
「多項式 f(x) 倍する操作」を単に f(x),「x で微分する操作」を ∂ とおくと
∂x−x∂=1
となる。
ここで「おかしい!」と思った人もいるかもしれません。そもそも ∂x=dxdx=1 だから計算結果は 1−x∂ であるはずだ! と思ったあなた,良い間違いです。
ワイル代数の元はそのものだけでは効果を発揮しないのです。関数 f に作用して初めて意味があります。ゆえに ∂x−x∂ という元は
f↦∂(xf)−x∂(f)
という操作を意味している元なのです。
積の微分公式を思い出して計算すると
dxd(xf)−xdxd(f)=dxdxf+xdxdf−xdxdf=f
と計算され,ワイル代数の関係式として
∂x−x∂=1
が得られるのです。
この関係を想うと N+1 回目で裏,N+2 回目で表が出た場合,偶奇が変わらないことが自明に感じられます。
さて,ワイル代数には他にも重要な性質が成り立ちます。
任意のワイル代数の元 D は
D=∑cn,mxn(∂)m
の形で表すことができる。ただし cn,m∈C である。
交換関係を繰り返せば x を左に寄せることができることを意味します。左に x がある = 最後に裏を出す = x=0 で偶数である ということですから,この形に表現しなおしたとき,(∂)m だけの項がどれくらいあるのか数えると,fN(0) の様子が分かります。
議論
では,ワイル代数の性質を使いながら議論してみみあしょう。
ステップ1:交換関係で計算
表ばかり出す→裏ばかり出す という状況を,ステップ1の交換関係を通して調べてみます。
ステップ2
a を正整数として,この交換関係を用いると
∂ax(f)=∂a−1x∂(f)+∂a−1(f)=(∂a−2x∂+∂a−2)∂(f)+∂a−1(f)=⋯=x∂a(f)+a∂a−1(f)
を得る。
正整数 a,b に対して,同様に計算する。
∂axb(f)=(x∂a+a∂a−1)xb−1(f)=x∂axb−1+ax∂a−1xb−2(f)+a(a−1)∂a−2xb−2(f)=⋯=x⋅(x,∂ の多項式) (f)+a(a−1)⋯(a−b+1)∂b−n(f)
を得る。
よって
∂axb(ex)(0)=a(a−1)⋯(a−b+1)
と計算される。
同様の計算をすると ∂axb(f)=x⋅(x,∂ の多項式) (f) と計算されるため,x=0 を代入すると 0 になる。
以上の議論から,表を連続で a 回出す→裏を連続で b=N−a 回出す場合,a<b の場合は fN(0)=0 になる。また,a>b≧2 の場合,
a(a−1)⋯(a−b+1)=aPb
は連続する2つ以上の数の積であるため,偶数になる。
以上より a=N−1,b=1 で,N−1 が奇数であるの場合のみ fN(0) が奇数になる。
ステップ3
当然,考えるパターンは上記のものだけではありません。
他のパターンの考察も行います。
ステップ3
ステップ2のときと同様にして
∂a1xb1⋯∂anxbn∂A(ex)(0)
(a1,⋯,an,b1,⋯,bn=0,n≧0)が奇数となる場合を考察する。なお,A は 0 であってもよい。
ステップ2の議論から a1 は奇数で b1=1 である必要がある。
このとき,
∂a1x∂a2zb2=x∂a1+a2x+a1∂a1+a2−1xb2
となるため,x=0 を代入することを考えれば2項目のみ考えればよく,a1+a2−1 が奇数で b2=1 である必要がある。a1 が奇数であることと合わせると a2 が奇数であることが条件である。
以上帰納的に議論をすることで条件,
- n≧0 で a1,a2,⋯,an が奇数,b1=b2=⋯=bn=1
を満たす場合,奇数となる。
※ n=0 の場合は {a1,⋯,an,b1,⋯,bn} は空となり自動的に条件を満たすものとする。
最後の表現は見慣れないかもしれませんが,事実 ak,bk が存在しない場合は fN(x)=∂N(ex)=ex となり,実際に fN(0) が奇数になります。
ステップ4:別の数え上げへの帰着
ステップ3で得られた条件を用いて別の問題に書き換えましょう。
ステップ4
ck=ak+1 (1≦l≦k) とおく。{ck} を用いると条件は
- n≧0,c1,c2,⋯,cn が偶数,A は非負整数で c1+c2+⋯+cn=N−A である。(n=0 の場合,左辺は 0 として扱う)
である。よってこのような偶数列を数え上げればよい。
∗∗∗
このとき N=2M (M≧1) と表すことができる。このとき,A も偶数になるため A=2B と表す。
辺々を2で割ることにより
- n≧0,d1,d2,⋯,dn が正の整数,B は非負整数で d1+d2+⋯+dn=M−B である。(n=0 の場合,左辺は 0 として扱う)
を満たす (d1,d2,⋯,dn,B) の個数を調べればよい。
n>0,B<M を固定したとき,和が M−B となる (d1,⋯,dn) の組は M−B−1Cn−1 である。
n についての和を取ることで B<M を固定したときに条件を満たす数の組の個数が分かる。計算すると
n=1∑M−BM−B−1Cn−1=2N−B−1
である。B=M のとき,条件を満たすものは 1 組である。
各 B について和を取ることで,条件を満たす (d1,d2,⋯,dn,B) の組み合わせは
S2M=1+B=0∑M−12M−B−1=2M
であることが分かる。
先ほど同様に N=2M+1 (M≧0),A=2B+1 と表すことができる。
この場合も条件は
- n≧0,d1,d2,⋯,dn が正の整数,B は非負整数で d1+d2+⋯+dn=M−B である。(n=0 の場合,左辺は 0 として扱う)
である。M≧1 のとき,同様に計算すると
S2M+1=2M
となる。M=0 の場合は B=1 の1通りのみであるため,上の式は条件を含む。
ステップ5:まとめ
ステップ5
ステップ4より求める確率 pN は次のようになる。
- N が偶数の場合
pN=2NSN=2N22N=22N1
- N が奇数の場合
pN=2NSN=2N22N−1=22N+11
だいぶ遠回りになってしまいましたね。とはいえ,微分演算子であることを中心に据えて議論することができました。
発展
以下,代数学の基本的な言葉を仮定して,ワイル代数の展望を説明します。
ワイル代数は,もちろん多変数に拡張することができます。こうすることで n 変数の「微分」全体の集合を考察することができます。これをアルファベットの D を用いて D (Dn) と書きます。
※ 微分演算子と混ざりやすいですが D と書くこともあります。より抽象度の高いレベルで考えるときのみ D と書く人もいます。
D の元は自然に微分方程式と対応付けられます。実際,x−dxd という元を取ってきた場合,xf−dxdf=0 と微分方程式を作ることができますし,逆もまた然りです。
D は自然に非可換環の構造を持つため,D 上の加群構造を考えることができます。これは D の元がスカラー倍で作用するベクトル空間のようなものです。
こうした集合を D 加群と呼びます。
D 加群の性質を深く調べ,代数・幾何・解析の世界をより深く結びつけた人物こそ,先日アーベル賞を受賞された京都大学名誉教授柏原正樹先生です。
柏原先生がちょうど今年アーベル賞を受賞されていたところでこの出題です。いえ,さすがに深読みしすぎですね(笑)
D 加群の理論を勉強するなら,池祐一先生のノート・竹内潔先生の『D加群』・堀田先生と谷崎先生の『代数群とD加群』(とその英訳)がおすすめです。