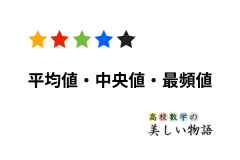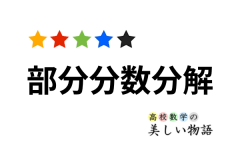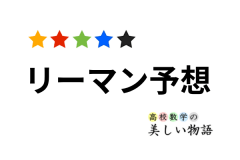位相空間論の基礎~多項式写像を用いた開・閉集合の証明
更新
を 変数多項式とする。
このとき は の閉集合である。
この記事では開集合・閉集合の証明方法として,多項式写像を用いたものを紹介します。
連続写像の復習
連続写像の復習
を連続写像とする。
-
開部分集合 に対して は の開部分集合である。(これを定義として用いられることもある)
-
閉部分集合 に対して は の閉部分集合である。
→ 位相空間論への第一歩~連続関数とは何なのか? いくつかの重要な定義
多項式写像は連続写像です。よって多項式写像の逆像を考えると開集合・閉集合であることを証明できます。
簡単な例
簡単な例
多項式写像は連続写像です。また ()において,1点集合は閉部分集合になります。
よって,多項式写像で1点集合( などがよい)逆像を取ると閉集合であることが示されます。
円 は の閉部分集合である。
を と定める。この写像は連続写像である。
である。 は閉部分集合であるため, は の閉部分集合である。
で 複素行列を表す。
一般線型群 は の開部分集合である。
特殊線型群 は の閉部分集合である。
行列式 は,行列 に対して と成分の多項式で書くことができる。→ 行列式の基本的な定義・性質・意味
※ 例えば だと と書ける。
よって, は多項式写像である。
である。( の補集合)は開部分集合であるため は の開部分集合である。
より は の閉部分集合である。
応用例
応用例
を により定める。 は転置行列であるため,各成分は の多項式で表される。また行列の積も成分の多項式で表されるため, の各成分は の多項式で表される。よって は連続写像である。
ここで は閉部分集合であるため, は閉部分集合である。
複素共役について
複素共役について
において,複素共役を取る操作 は連続写像です。よって,複素共役を用いて定義される の部分集合の開・閉判定も同様に行うことができます。
例えば,元の行列 に対して,複素共役と転置を行った行列 (随伴行列)により定義されるユニタリ群 が の閉部分集合であることは,直交群と例と同様に証明することができます。
多様体(微分構造が入った図形)の判定にも多項式写像を用いることがあります。