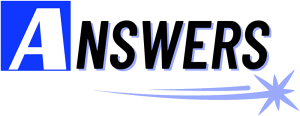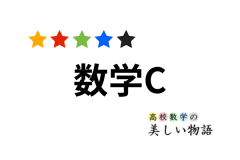解答に入る前に、平面ベクトルと複素数について対応を述べておきます。
平面ベクトルと複素数
点 A の位置ベクトル OA が
OA=(xAyA)
を満たすとき、この点 A は複素数平面における
α=xA+iyA
なる α が示す点と同一位置の点になる。(つまり、平面ベクトルと複素数平面を重ねたとき、A と α が示す点は重なる。)
さらに、点 B に対して対応する複素数 β は
OB=(xByB),β=xB+iyB
の様に定義できる。ここから、
AB=(xB−xAyB−yA),β−α=(xB−xA)+i(yB−yA)
であることが分かるため、AB に対応する複素数は β−α と言える。
では、上記を念頭に置いて考えてみましょう。
(1)
点 Pn に対応する複素数を zn とする。
P0P1=(10)
であることから、P0P1 に対応する複素数は
z1−z0=1+0i=cos(0)+isin(0)
である。さて、条件(ii)を複素数平面の目線から捉え直すと、
『P1P2 に対応する複素数、即ち z2−z1 は z1−z0 を r倍拡大, 120度回転して得られる』
ということである。したがって
z2−z1=(z1−z0)×r[cos(32π)+isin(32π)]
が成り立つ。同様にして、
z3−z2=(z2−z1)×r[cos(32π)+isin(32π)]=(z1−z0)×r2[cos(34π)+isin(34π)]
これを計算することにより
z3−z2=−r2(21+23i)
となるため、対応するベクトルP2P3は
P2P3=−2r2(13)
であると分かる。
(2)
条件(ii)より、3回操作で大きさは r3 倍、向きは(360度回転の結果として)元通りとなるから
PiPi+1=r3Pi+3Pi+4
が成り立つ。したがって、
P0P3m=P0P1+P1P2+P2P3+⋯+P3m−3P3m−2+P3m−2P3m−1+P3m−1P3m=(1+r3+⋯+r3(m−1))(P0P1+P1P2+P2P3)
と分かる。このベクトルは P3m 位置ベクトルなので、この x,y成分がそのまま座標となる。(具体的な計算は略。)
(3)
(2)の係数部分 (1+r3+⋯+r3(m−1)) について m→∞ の極限を考える。これを無限等比級数と捉えれば
1+r3+⋯=k=1∑∞r3(k−1)=1−r31
と変形できる。よって収束点の位置ベクトルは
1−r31(P0P1+P1P2+P2P3)
と書ける。
少し雑な書き方ですが、エッセンスは取り出せていると思います。