数学の質問です。
恒等式の性質で「が恒等式等式が個の異なるの値に対して成り立つ」と言うものがありますが、この性質の証明(高校生でも理解できるもの)を知って居る方がいらっしゃいましたら教えて頂けるとありがたいです。
回答宜しく願います。
ベストアンサー

質問での を、 次の多項式 とします。
また、
恒等式
すなわち …
を満たす相異なる 個の実数 を、
とおくと、これらの実数は を満たすので、因数定理より、 は
のそれぞれで割り切れます。
したがって、は、実数 を用いて、以下のように表すことができます。これは 次関数です。
…
しかし、 は 次関数、 も 次関数であるので、 は必ず 次以下の関数ですから、 のように 次関数で表されるはずがありません。よって、
だと 次関数になってしまう
となります。したがって より、
すなわち、
が成り立ちます。(終)
訂正 3行目の「恒等式」は、「恒等式」ではなく、「方程式」です。
恒等式は にどんな値を入れても成り立ちますが、この方程式は特定の についてのみ成り立ちます(結局恒等式ということが分かりますが、この段階ではまだただの方程式)。すみません。
質問なのですが、「を満たす異なる個のの値をと置くと、」とありますが、なぜ、の値をと置くのでしょうか?これから証明しよう!と言うことはは単に方程式だと言う認識でしかなく、は次以下なので、としか置けないと言う風に思うのですが、、、??
私は何を勘違いして居るんでしょうか?
返信ありがとうございます。
すみません、「方程式」という表現を使ってしまったのですが、この表現だと「 について解く」という意味合いになってしまうので、私のミスにより勘違いを起こしているのだと思います。シンプルに「等式」という表現を使うべきでした。m(_ _)m ↓
逆向きの存在を忘れていたのですが、この命題
の気持ちとしては、
「普通なら等式を満たす がただ 個存在するはずなのに、この場合は 個も存在している。
これってもしかして、どんな を入れても成り立つ(言うならば無限個の相異なる について成り立つ)恒等式なんじゃないか?」
といった感じです。
ちなみに逆向きの命題を考えると、 が恒等式のときは、この等式を満たす は無限に存在するので、等式は 個(かそれ以上)の について成り立ちます。
ごめんなさい、私自身も矢印の向きのことが頭から抜けて居ました、、、
因みに、Cocoa9さんにしていただいた証明はどちら向きの矢印ですか?なんか色々こんがらがっちゃって、、、
最初の方の というのは単に2つの関数をイコールで結んだだけのもので、、これが 個の に対して成り立つということなので、書き換えると、
が成り立つということです。
ここから先にした説明をしていくと、次のことがわかるのです。
これが最後の方の の意味です。
2つ目質問の回答を含めたきちんとした説明を後ほど追加しようと思います。
Cocoa9さん!
回答欄では文字数制限はない様ですが、返信欄では文字制限がある見たいなんです。幾つかに分割して投稿して頂ければと思います。お願いします。<(_ _)>
なぜ と表せるかというのは、簡単な例を挙げると理解しやすいと思います。(前半は簡単と感じれば読み飛ばして問題ありません)
ここからは説明のために、
と置きます。
の場合を考えてみましょう。 はそれぞれ2次関数、 は(2次関数)-(2次関数)ですので2次以下の関数ですね。
まずは、 が相異なる 個の に対して成り立つときを考えます。このとき、
ですね。 を用いてこのことを表すと、
です。
このとき、因数定理より、 は で割り切れて2次(以下の)関数なので、
と置けるのは理解できると思いますし、のときに となるような2次関数のグラフを想像してみてもわかるかもしれません。
では本題の、 が相異なる 個の に対して成り立つときを考えます。個のときと同様、
となります。もしかしたら、ここで が3次関数になんてなるわけないのに
といきなり置いてしまうことに違和感を感じるのかもしれません。
しかし、この式は見た目上3次関数になってしまうように見えますが、ある特別な場合のみきちんと2次以下の関数になる場合があるのです。それが、前の回答で述べたの場合なのです。このとき、という関数になり、定数関数(0次関数)となり確かに2次以下の関数になっていますね。
以上の理由から、 という関数になり、という恒等式が成り立つのです。
今回は の場合で説明しましたが、これを一般化することで証明を得ることができるはずです。
長くなってしまいましたが、分からない・分かりにくい点があれば教えてください。
文字数制限の件、教えてくださりありがとうございました。
因数定理を使うところの考え方?は分かりました。ありがとうございます。
しかし、10枚目の返信(Cocoa9さんの2023/8/15 9:14の返信)に就いてまだ分からないことがあります。が成り立ったとしても、となるかも知れないですよね?そうするととが一致しないのではないのでしょうか?なぜとが一致すると言い切れるのでしょうか?
結論から申し上げますと、 となるようなことはありません。 が成り立っているという時点で、すでに前に示したように、 と が全く同じ関数であるということが言えるからです。
もし仮に となってしまうような実数 が見つかってしまう場合は、 と は違う関数であり、恒等式が成り立ちませんから、 を満たすような は 個も存在しません。
以上より、
という2つのことは両立しないので、質問のようなことは起こり得ません。
の場合でグラフを使って考えると、
2つの2次関数 と のグラフの共有点を3つ定める を満たす を定める)と、2次関数 はどのような形の関数が決まり、2つの関数は一致しますよね。なぜなら、
2次関数は通る点を3つ決めると定まるので。
そうすると、2つは同じグラフですから、同じ 座標で違う値を取るということはないわけです。
これが、 となる が存在しないということのグラフ的な意味です。
と の(より正確には と グラフが一致するというのは、 という恒等式が成り立つことと同値です。恒等式が成り立つとは2つの関数が全く同じということですので。
ですから、恒等式が成り立つ証明とグラフが一致する証明は同じことです。
グラフの説明はあくまで身近な例を持ってきたというだけです、混乱をさせてしまってすみません。
Cocoa9さんの説明を読んで行く内に私もそれらが同値であることに気付いたのですが、10枚目の返信(Cocoa9さんの2023/8/15 9:14の返信)でCocoa9さんがならばと言う旨のことをおっしゃっていましたが、この関係性が良く分かりません。私は何か見落として居るのでしょうか?
というのは、kakko_pnさんの最初の質問の、「等式 が 個の相異なる に対して成り立つ」ということの式を使った言い換えです。これを因数定理を使用して証明すると、恒等式 が成り立つことがわかる、ということです。
これらは
というような矢印で繋がっています。
という回答で合っているでしょうか?わからないことがあればお聞きください。
えーっと、因数定理を使って計算した後のでが恒等式だと分かるのはなぜですか?最初に提示されたと因数定理を使って計算した後のは何が違うんでしょうか?形が同じなので、因数定理を使って計算した後のが自分から見ると只の等式にしか見えないのですが、、、?
いえ、それはCocoa9さんの返信を読んでから返信したものです!
良く分からなくて、、、
教えて下さい!
「良く分からなくて、、、」と言うのはCocoa9さんのおっしゃっていることが分からないのではなく、2つ前の返信で言ったことに就いてです、、、
グラフも交えて説明してみました。
最初の方の因数定理の前の は、ことがわかっていて、他の値で成り立つかどうか、わけです。
そこで、全ての値でで成り立つかどうかがわかるように、 に因数定理を使い、 と置くことで、 が どのような関数なのかを知ることができます。
その結果、全ての の値において ということがわかります。
最終的に、 であったので、、恒等式となるのです。
因数定理で を置くと全ての の値でどのような関数かがわかるようになるとありますが、これは例を出すと伝わるかもしれません。
例えば、傾きが2で点(1,3)を通る一次関数は、 と置くことができます。こうすることで、 に好きな値を代入して 座標を求めるなど、全ての での情報を知ることができます。傾きの通る点という少ない情報から全ての情報を得ることができるのです。

シェアしよう!
そのほかの回答(1件)
こんにちは.お答えします.
が で成立するとしましょう.
とおきます.このとき は高々 次の式です.
仮定より ですので,因数定理より,
となります.
とすると が 次式になってしまいます.
これらは矛盾ですので となり, が得られます.
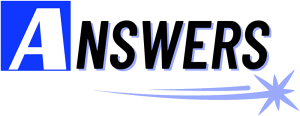



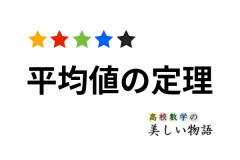


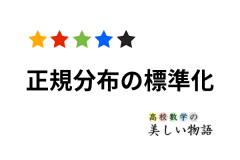

質問者からのお礼コメント
何度も何度もありがとうございます!!!
感謝しかありません!!😄😄😄