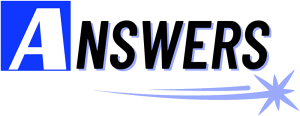抵抗を変えると電圧は変わるが、電流そのものは変わらない。
①しかし、「〇Vの電圧をかけて〇A流れた。抵抗は?」という問題文が成り立つのはなぜ?
②電流は何に影響を受けるのか?例えば、電気の契約の際の40Aと50Aでは、電気の流れる量をどうやって変えているのか。
ベストアンサー

一つ一ついきましょう。
①抵抗を変えたとき、電圧も電流も変わる例は存在します。オームの法則よりR=V/Iですが、この式より例えば一般的に電圧が二倍になれば電流も二倍になることが分かります。おそらく、直列接続の回路の知識が悪さをしていると思いますが、【回路の性質があってオームの法則がある】のではなく、【オームの法則があって回路の性質がある】ことになります。ですので、一般的な問題は、このオームの法則に基づいた時にいったい全体電圧とか電流とか抵抗はいくらなんたい?と聞いていることになります。(※逆に直列接続とか並列接続だとか回路自体はこの段階では一意に定まりません。)
②アンペアブレーカーというものがあり、これを使って家庭に入る電流量を調整しています。電流とは【単位時間に流れる電荷の量】として定義されますが、この【単位時間に流れる電荷の量】をアンペアブレーカーを用いて調節していることになります。その他にも変圧器というものがあり、これを用いて電圧を変えて電流をそれに対応させる形で変化させていく方法もあります。