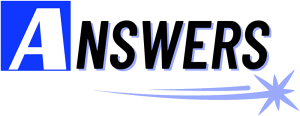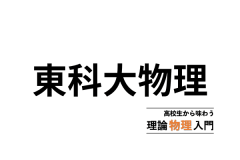熱力学で、気体がされた仕事が分かりません。
気体に対してなされた仕事の定義が分からず、また、力学の範囲では、された仕事とエネルギーの関係は理解しているのですが、した仕事とエネルギーの関係など習っていないので、当たり前のようにした仕事がされた仕事を-1倍したものになる理由も分かりません。
ベストアンサー

「した仕事がされた仕事を-1倍したものになる理由」は、「した仕事とエネルギーの関係」から導かれるものではなく、受け入れるものですね。
たとえば10Jのエネルギーを水に加えた(水に10Jの仕事をした)とき、水の視点から見たら「水は10Jの仕事をされて」います。
厄介なのはここからで、「水がした仕事」を求めろ、と言われることがあるわけですが、ここで「水は-10Jの仕事をして」いる、という答えが正解になります。
「水は10Jの仕事をされた」⇔「水は-10Jの仕事をした」
まずこれを受け入れます。
気体は「された仕事」と「した仕事」を同じ文字で表現することが多いです。
例えば気体が3/2PVの仕事をされ、PVの仕事をしたとき、「合計で気体がされた仕事W」は、
「PVの仕事をした」を「-PVの仕事をされた」と言い換えて、
W = 3/2PV - PV = 1/2PV
とします。
仕事がするされるという日本語についての理解が深まったなら幸いです。よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。
大学以降では説明できるものなのでしょうか、それとも物理自体が受け入れるものなのでしょうか。
面倒臭い質問になってしまい申し訳ありません。
2つお答えしますね。
1. おそらく大学物理の知識を得たところで説明できるものではなく、受け入れるものである
2. 私がどう受け入れているか
1. について、大学では高校より進んだ微積などの数学を使い、物理的現象を説明していくことになると思いますが、微積とか難しい数学とかがわかったから理解できる、ということではないと思います。(私も大学に入ったわけではないので、わかりませんが)
2. について、私は
自然界にとっては「する仕事」と「される仕事」の区別はあまり重要ではなく、これらの名前は人間が理解する手助けとなるよう便宜上つけたものである
と理解しています。
気体の場合、
気体が膨張して外部の物体を動かす場合に「正の仕事をする」あるいは「負の仕事をされる」、
気体が力を加えられて収縮する場合に「負の仕事をする」あるいは「正の仕事をされる」
などと言うように決まっている(物理自体が受け入れている)という理解で大丈夫だと思います。