有効数字の計算についての質問です。
特に化学や物理の記述試験での解答について2つ質問があります。
1.有効数字2桁で答える問題では、
①途中計算は4桁目を切り捨て3桁目まで出して計算する。
②解答は3桁目を四捨五入し2桁で答える。
この方法で合っていますか?
2.例えば「分子量2.0の気体が3.0molあるときの質量を有効数字2桁で求めよ。」という問題が出たとき、計算過程で、2×3=6, 6.0gというように、計算過程では有効数字の表示を略し、最後の解答だけ有効数字で書くと減点される可能性はありますか?
細かい所かもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。
ベストアンサー

計算方法はそれでよいと思います。
計算ミスを少なくするためのポイントとしては、かけ算は計算せずにそのまま を用いて書き、最後に計算すること、割り算は最後に 回のみ行うようにしましょう。
最後の割り算以外は有効数字を気にしないで解いてもよいですね。
(化学で本当に面倒な計算の場合は早めに桁を切り上げるのももちろんOKです)
かけ算を行わない理由としては、約分ができる可能性があることです。
割り算を行わない理由は、割り切れない場合があってそれが面倒だからです。最後に行うことで、有効数字に気を付けて四捨五入すればよいですね。
有効数字についてのルールは、特に大学の実験の授業で学ぶと思いますが、以下に説明します。
そもそも、有効数字とは何でしょうか。有効な数字のことですから、値にある程度信頼性があることを保証する数字のことです。
たとえば、長さが と、 を比較してみましょう。
というと、小数第 位まで信頼性があるということであり、 ですね。
一方、 というと、小数第 位まで信頼性があるということであり、 です。
後者の方が圧倒的に精度が高く、有効数字が多いということは信頼性が高いということですね。
計算のルールでは、和と差は「位の大きい方」に合わせます。積と商は「桁数の少ない方」に合わせます。
信頼性が保証できるのはどこまでかを考えれば、それほど理解しづらいことはないと思います。高校の理系科目でこの知識が要求されることはないので、詳しくは大学で学んでください。
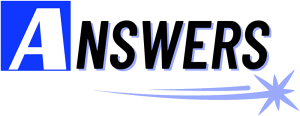



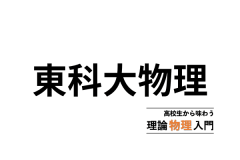




質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。
有効数字の計算についてよく理解できました。2番の質問について、大学入試での解答で、計算途中の有効数字の表記は省略してもよろしいのでしょうか。どなたか返信していただけると嬉しいです。