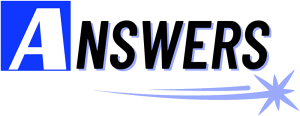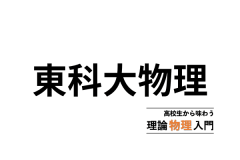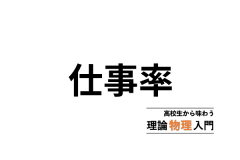仕事の原理はなぜ成り立ちますか?
高校の教科書にはてこと動滑車の例をあげて必要な力は減るがかかる距離がそのぶん増えるというような説明がされていたのですが、仕事の定義は力と力を受けた物体の変位の内積ではないのですか?
増えた距離はかけた力が動いたという話で仕事とは無関係じゃないんでしょうか
ベストアンサー

kodawaruhitoさんの仰るように、一般に仕事は「物体にかかる力」と「物体の変位」の内積です。
ただ、これを単に仕事とは言わずに、「された仕事」と言う時があります。結局は「与えられたエネルギー」とほとんど意味は変わりません。
これに対して、エネルギー保存則からわかるように、エネルギーを与えられる物体がある時、エネルギーを与える存在も必要です。すなわち、物体が仕事された時、他の何かが「仕事をしている」ということです。
物体の最終的な状態が一緒ならば、この「する仕事」(与えるエネルギー)は変わらないよねっていうのが、「仕事の原理」の意味です。
いつもは「仕事」といえば、力を受ける側のことを言いますが、今回は力を与える側に注目しているって言うことですね。
ちなみにですが、仕事の原理は物理学的にはエネルギー保存則の1種であり、そんなに重要な考え方じゃない気がします。仕事やエネルギーについてまだよくわかっていない中学生に向けた説明だと個人的には思っています。
なので、高校物理からは、この仕事の原理は単にエネルギー保存則をなんか特殊な条件下で考えたものぐらいに思った方がいいと思います。
エネルギー保存から説明できるのは理解できるのですが、仕事の定義からすると、した仕事は小さくなるように思えてしまいます。
どこかで仕事を力の作用点の変位で定義するというようなことを見たことがあるのですがこっちの定義が回転も含めた定義になっているのでしょうか。
物体の変位での定義は質点でしか定義できず、てこのような回転ではうまく定義できないのかなぁなどと考えてみたのですが間違っているでしょうか