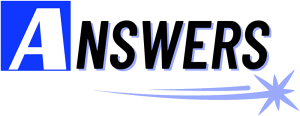化学基礎の酸と塩基
弱酸の塩の水溶液が塩基性を示すのはなぜですか?
以前に、以下のような解説を聞きました。
「弱酸の塩、例えばCH3COONaについて考える。酢酸ナトリウムは酢酸と水酸化ナトリウムの中和反応により出来ていて、酢酸は弱酸なので、酢酸は水溶液中で1部だけ電離している状態が理想である。だから酢酸ナトリウムの酢酸イオンはその理想な状態に戻ろうして、一部がH2Oの水素イオンとくっつくことで(加水分解)、水酸化物イオンが生じるので、その水溶液は塩基性となる。」
これで一応理解できたのですが、疑問が湧きました。
中和滴定の時にこういうことを聞きました。
「弱酸の水溶液と強塩基の水溶液だとしても、弱酸の電離度を考慮しなくてもいいのは、水酸化物イオンが十分にあれば弱酸の水素イオンはすべて電離してH2Oになるからだ。」
これは、最初の話にも当てはまらないのですか?
酢酸ナトリウムの酢酸イオンがH2Oの水素イオンとくっついて、液性が塩基性になっても、OH-がそのへんにたくさん漂ってるので、また電離してすべてH2Oになるんじゃないかと思いました。
ベストアンサー

この話は化学平衡の話を知るとすっきりと理解できます。
酢酸の電離の反応が起こる時実は逆の反応、つまりイオンがくっついて酢酸に戻る反応も起こっているのですが、最初は電離の反応のほうがスピードが速いため電離度の値まで電離しきるまで電離の反応が起こることになります。電離とその逆の反応を合わせた全体での反応のスピードは酢酸、酢酸イオン、水素イオンの濃度のバランスによって決まり電離とその逆の反応のスピードが同じになるような、濃度のバランスがとれた状態(質問者さんの聞いた解説でいうところの理想の状態)で電離の状態が落ち着くことになります。この濃度のバランスを示すのが、酢酸(一般的に言えば反応物)の濃度を酢酸イオンの濃度と水素イオン(一般的に言えば生成物)の濃度で割った値で、これが一定の値になるところまで反応が進みます。
同様のことが水の電離にもいえて、このことから中和の反応が起こるときは、水素イオンと水酸化物イオンの濃度がどちらも高く、それを解消するようにイオンが水になります。このとき水素イオンの濃度が下がっていくため酢酸の電離でのさっき言った一定の値を保つよう反応が進み酢酸が水素イオンを出し切るところまで反応が進みます。
一方酢酸ナトリウムの話では水中に酢酸イオンが大量に出ると酢酸の電離と電離の反応のバランスを保つように、つまり一定の値をたもつように反応が進むことになるため、電離の逆の反応が起こりますが、水素イオンが足りないため、水が電離して水酸化物イオンが残ることになります。このときどこまで酢酸に戻る反応が起こるかももちろん酢酸の電離、水の電離の反応における一定の値を保つ状態で反応が落ち着くため、酢酸イオンは全て酢酸に戻るわけではなく酢酸と水の電離それぞれの反応のバランスが保たれた、少し塩基性に偏った状態で反応が落ち着くことになります。
非常に長い文章になり、分かり辛い説明になってしまいましたので、これでわからなければ、化学平衡について調べていただければ納得できるかと思います。
化学平衡は化学基礎ではなく高校の範囲の化学になりますが自分は化学平衡を習って初めてすっきり理解ができたので、きちんと理解したいなら学んでみることをおススメします。
(当方高校生につき正確性、厳密性は保証しかねますので悪しからず)