物理の質問です。
回路中で導体(導線)などは等電位ですが、等電位なのにどうして電流が流れる=電子が動く=電子に力が働くのでしょうか?
ベストアンサー

削除済みユーザー
導体の各部分が等電位であるとは、その導体内部に存在する電子が等しいエネルギーレベルを持つということです。しかし、導体全体が等電位であるとは限らず、導体の一端から他端への電位差が存在する場合、電子はその電位差に応じて導体内部の電位差を無くすために移動します。
わからない点が合ったら遠慮なく言ってください。
返信ありがとうございます
→導体の一端から他端への電位差が存在する場合、電子はその電位差に応じて導体内部の電位差を無くすために移動します。
1、結局電子は2端の電位差によって生じた電場から力を受けて移動するということなのでしょうか?
2、それとも力を受けていないのでしょうか。
3、力を受けてない場合電子は力を受けず速度を持つことができるということなので、電子が持つ力学的エネルギーは外部から仕事をしなくても増大させることができるということですか?
削除済みユーザー
1、結局電子は2端の電位差によって生じた電場から力を受けて移動するということなのでしょうか?
→その解釈であっています。
2、それとも力を受けていないのでしょうか。
→受けています。
ありがとうございます!!
つまり
・電位差が生じているのは端点のみ。
・それを繋ぐ導線は等電位
ということですね。
この場合、
2端点を導線でつなぐと2端点の電位差が電場を導線中に生じさせて導体中を等電位ではなくしてしまうように思われます。
電場中に金属板を入れたときのように電子が電場を打ち消すように動いて(偏って分布して)とどまってくれればいいのですが(静電誘導)、電池を繋いだ回路中では電子はとどまらず(一様に分布したまま)流れています。(電流のイメージから)
どのようにして導体中だけが等電位となってしまうのでしょうか?
長らく質問にご付き合いいただき本当にありがとうございます。
上の考え方が間違ってたらビシバシ批判してください!大歓迎です!
削除済みユーザー
つまり
・電位差が生じているのは端点のみ。
・それを繋ぐ導線は等電位
ということですね。
→その解釈であっています。
電場中に金属板を入れたときのように電子が電場を打ち消すように動いて(偏って分布して)とどまってくれればいいのですが(静電誘導)
→導体内部に電位差が生じている間は、静電誘導が行われますので、次のような順で等電位になります。
・ 導体内部に電位差があると、電場が発生。
・ 電場によって、導体中の電子が電位差の向きに沿って動く。
・電子が動くことで、電位差が小さくなっていく。
・ 電位差が小さくなるにつれて、導体中の電荷の再分布が起こる。
・電荷の再分布によって、電場は小さくなる。
・最終的に、電位差がゼロになり、導体内部は等電位になる。
1,それは静電場の時だけでなく、回路中で電流が流れるときでも同様に、一部の電子が電場を打ち消すように静電誘導を誘起させられ、余った他の電子が流れることで電流が構成されているということでしょうか?
2,つまり回路にかける電圧を2倍にすると、静電誘導を起こす電子の数が増え、電流を構成する電子数が減るのに対し、電流の値、つまり単位時間当たりの通過電気量は増加するので、電子の速さは2倍よりおおきくになるであっていますか?
お手数かけて申し訳ありません。
お時間があればお願いします!
削除済みユーザー
1,それは静電場の時だけでなく、回路中で電流が流れるときでも同様に、一部の電子が電場を打ち消すように静電誘導を誘起させられ、余った他の電子が流れることで電流が構成されているということでしょうか?
→その解釈であっています。
2,つまり回路にかける電圧を2倍にすると、静電誘導を起こす電子の数が増え、電流を構成する電子数が減るのに対し、電流の値、つまり単位時間当たりの通過電気量は増加するので、電子の速さは2倍よりおおきくになるであっていますか?
→その解釈であっています。
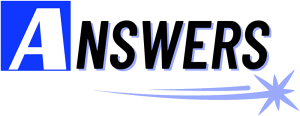








質問者からのお礼コメント
遅れて申し訳ありません。
ありがとうございます!
非常に納得できました