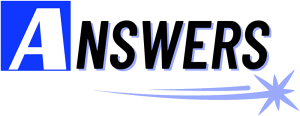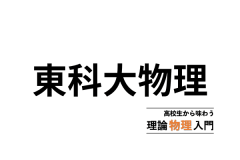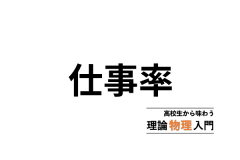物理 仕事
授業聞けてないのでこちらの問題解答解説して頂けないでしょうか。

ベストアンサー

まず、仕事の概念について簡単に復習しておきましょう。
ある力が物体に対してする仕事は以下の様に書かれます。
ここで、は物体の変位の大きさ、は力と物体の進む方向の間に発生する角度のことです。今回の問題では、は30に当たりますね。の値次第で仕事は正にも負にもなりますから注意しましょう。
もう少し数学的に書くなら、ベクトルの内積を用いて
ともできます。(ベクトルを習っていなければ無視して構いません。)
また、仕事率は(今のところ)以下の様に書けます。
ここでは物体の速さであり、は速度の向きと力の向きの間の角です。
これもベクトルを用いて表現することが出来て、
となります。
*回答の中にあるは、ニアリーイコールみたいなもの。
(1)
鉛直方向の力のつり合いを考えれば良い。力の鉛直成分は上向きにだから、垂直抗力をとして
kg、N、m/sであり、
であるので、これを代入してやれば
と分かる。(普通にやれば9.6[N]。有効数字的には10[N]の方が良いと思う。)
また、重力はのことなので、
と分かる。(これも有効数字的な議論がある。)
(2)
仕事の式を考えれば、重力と垂直抗力のする仕事は明らかに0。
(なぜなら、物体の進む方向と上の2力は直交しており、)
力に関しても仕事の式で計算すれば良く、この仕事をとすると
ここで
なのでを用いて
と分かる。
(3)
本問の速度をとすれば
であるため、仕事率の式から
これを計算して
となる。
冒頭に示した仕事は(実は)厳密な定義ではありません。高校レベルではほとんど冒頭の式で十分ですが、もう少し先に行くとこれではダメになってきます。もし興味があれば、数学をある程度頑張った上で厳密な定義の理解にトライしてみてください。(とはいえ、忙しい高校生がやることでは無いかも知れません。)
途中有効数字の話をしましたが、もしこの辺の話が苦手なら以下のサイトがおすすめです。
https://juken-mikata.net/how-to/chemistry/yuukousuuji.html
また、仕事率の計算の際にはとして計算した後四捨五入しました。余裕があれば、この意図についても考えてみてください。