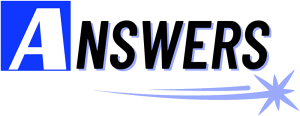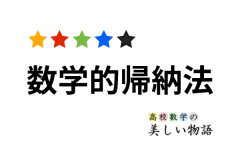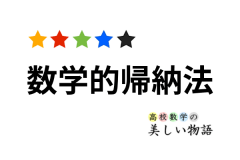解決済み
これの(2)が帰納法らしいのですがわかりません。
黄色傍線部なんですけど、Pk+1(m)となるとき、例えば、k-4回目くらいにはもう赤玉がm個であとの5回は白玉みたいな場合もあると思うんですけど、なぜ黄色線部の2つの場合しかないのか教えて欲しいです。
あとこういう問題で、座標平面に落とし込もう!っていう発想がなんで思いつくのか分からないんですけど、この問題は座標平面に落とし込んでやろう!って見極めるポイント的なものがあるんでしょうか。

ベストアンサー

k-4回目くらいにはもう赤玉がm個であとの5回は白玉みたいな場合は、その時点から白玉が4回出たら、k-1回目で白玉があと一個出ればいい状態になりますよね?それって黄色い線で引いた部分の前半の場合にすでに含まれてるんですよ!
それから、図形的に解く判断ですが、正直この問題は図形的に解く必要ありません。この問題の⑴って全ての場合を実験してねっていう問題で、図形要らなくないですか?⑴の実験で1/n+1が答えになりそうっていう予想が立ったから、⑵で帰納法による証明をしようという、受験ではとても典型的でよく出る出題だと思います。
ちなみに、この問題はどこかの大学で2007年に出題された問題のようですが、この問題とほとんど同じ問題が2023年早稲田理工の大問2番に出てますね!