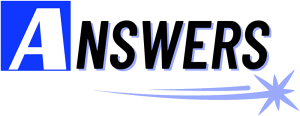化学の中和滴定の実験で正の誤差があらわれた考察を考えているんですが、空気中の二酸化炭素と反応して正の誤差があらわれたのは妥当性がありますか?
ベストアンサー

先に結論を言うと、「CO₂による誤差は理論的には妥当性はあるが、滴定への影響はほとんどない」です。
まず、条件によっては妥当性があります。
例:水酸化ナトリウム (NaOH) 溶液を滴定に用いる場合を考える。
この場合、滴定に使用した水酸化ナトリウム(NaOH)溶液が空気中の二酸化炭素(CO)と反応することで、水酸化物イオン(OH)が減少し、正の誤差が生じることがあります。
このときの反応式は以下の通りです:
この反応により、NaOH溶液中の有効なOHの量が減少し、滴定に必要なNaOH量(体積)が本来より多くなる。
したがって、以下の濃度の式で計算される酸の濃度 が、実際より高く見積もられる:
ここで、 が増えてしまうため、 が過大評価され、正の誤差が発生する。
そしてこの誤差が生まれる条件は、
○妥当性がある条件(COの影響が大きい場合)
・NaOH溶液を長時間空気中に放置した場合
・実験室の温度がかなり低くCOの溶解が進む場合
・低濃度のNaOH(例:0.05 mol/L)を使用した場合
○COの影響が無視できる条件
・NaOH溶液を直前に調製し、密栓していた場合
・滴定が短時間で終了した場合
---
しかし、現実的には後者の条件が満たされていることが多いです。
参考までに示すと、誤差の主な要因は重要度の順に次のようになります。
①終点判断におけるヒューマンエラー。
②ビュレットやメスシリンダーの目盛りの読み取りミス。
③濃度調製や使用する試薬の精度による誤差。
④CO₂との反応による誤差。
以上より、 と NaOH の反応は、理論的には正の誤差の原因として妥当性はあるが、化学実験においてその影響は極めて小さく、主な誤差要因とはなりにくいと言えます。