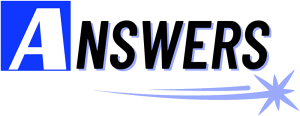高2地方の理系公立生です。
10月駿台の偏差値が
英語62国語72数学57英数国65英数60
京大工学部電気電子工学科B判定
1月進研の偏差値が
国語72数学71英語79 地理79物理75化学82
5教科79数英理理系77
京大工学部電気電子工学科Cでした。
これまでは他の旧帝大を目指していましたが先生にもっと上を目指すべきだと言われています。これまではあまり勉強していなかったのですが、今から本気で目指せば京大も現実的でしょうか。そして京大を目指すとしたら今は数学がまだまだだと自分では感じているのですが、何をやればいいでしょうか。
ベストアンサー

偏差値帯的には目指せます
京大の過去問はすでに解いたりしてますか?その感触を見てみるのもいいかもしれないですね
今後数学で何をやるかは、今使っている問題集がなにかにもよりますが、青チャートレベルの問題集が難なく解けるなら、バンバン過去問やるのがいいと思います。
シェアしよう!
そのほかの回答(2件)
数年前まで現役で高校数学教諭をしていた者です。私なら、質問者さんの先生同様、京大勧めたくなると思います。
理由は3つ。
・まだ本気出してなくてこの偏差値なら、本気出したらもっと伸び代があるから
・京大に興味があるなら、逆に今がラストチャンスだから(後から志望校を上げるのは本当に難しいので、本気でやめた方がいい)
・もし最終的に京大を受験しなかったとしても十分大きなメリットが得られるから
という点です。
質問者さんもおっしゃるとおり、まだまだ余力があるなら数学はもっと伸ばすべきでしょう。
京大数学は東大数学よりも難しいと言われており、通常なら小問が存在するような問題が大問1つのみで丸投げされる、という特徴的な出題のされ方をします。
これを攻略するためには数学の解き方のパターンや問題に対する理解度を今よりさらに上げる必要があります。そのためには今よりさらに勉強時間を数学に割く必要があり、かなりの負担になると思います。しかし逆に言えば、京大数学の訓練をしていれば他の問題が「小問の誘導なんてしてくれるんですか…!」と圧倒的に優しく感じることができます。
また、京大受験者には浪人生も多くライバルとして入ってくるので、3年生の模試でも同様に偏差値を伸ばしていけるか見ていくためにも、これからの模試の第一志望校に京大を書き続けることが大切になります。
ちなみに、今はまだ浪人生抜きの偏差値のはずなので(ちょっと自信がないので先生に確認してみてください!)、3年生になって最初の模試は判定が下がることが予想されます。そして、この判定は正直気にする必要はありません。
浪人生は最初からリーチがあるので判定が比較的出ますが伸び代も少ない。でも現役生は最後の最後までラストスパートの演習でグングン伸びていくので、共テの後、出願するまでは京大目指してていいと思いますよ。
もし京大がかなりのチャレンジになるのでしたら、滑り止めや、前(中)後期の受験校の組み合わせパターンをしっかり計画しておくことで、受験勉強にも専念できると思いますよ!
ただ、京大にすることによって受験に使う科目が大幅に増えることになるなら、自分の本気度とよく相談して決めた方が後悔が少ないかもしれませんね。
今ならまだ考える時間があります。逆に言えば今しかじっくり考えられません。
1年後、質問者さんが素敵な春を迎えられていますように。
京大理学部生です。
あまり無責任なことは言えませんが、質問者さんの偏差値や判定であればかなり余裕を持って合格できそうな気がします。ただ、京大型の問題で得点できるかというのはまた別問題なので、最終的には夏・秋の冠模試(京大オープン、京大実践)の判定を見て決められるのが良いかなと思います。
数学の勉強法についてですが、その偏差値であれば青チャート等の網羅系は終わらせているかと思います。その後にやる問題集としては、個人的には標準問題精巧が問題・解答の質ともにちょうど良かったのでオススメしておきます。(余裕で出来そうなら不要)
また、最近見つけたのですが、Mathematics MonsterというYouTubeチャンネルが東大・京大レベルの問題の解説動画を沢山アップして下さっていてオススメです。問題はその方のサイトに掲載されているようです。
過去問をやる際に問題が無くなってしまった場合は、古すぎる問題まで遡るよりは冠模試の過去問集の方が最近の傾向が反映されていてオススメです。
それでも得点が伸びないようでしたら、対面授業の方が得られるものが大きいので、各予備校の講習等も検討してみてください。
私の場合は、物理地学選択(※工学部は地学不可)だったのであまり参考にならないかもしれませんが、高3でオープンD、1浪でオープンB→実践C→オープンC→実践D(いずれも冠模試、オープンはDが1番下、実践はEが1番下)で、合格者平均点より少し上で合格しました。