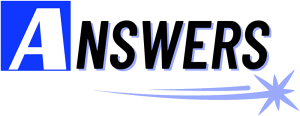中学古文の問題です。2番についてなのですが、答えがaになっていました。理由を教えてください。お願いします🙏

ベストアンサー

aの「の」だけが、現代語と同様の使い方です。それ以外は、現代語では「を」や「が」を使います。
それぞれについて、【古】古語(原文)、【現】現代語風、【訳】意訳(意味が通るように訳すこと)を載せておきます。
a
【古】あらぬ道の筵
【現】あらぬ道の筵
【訳】自分の専門(道)でない会合
b
【古】知らぬ道の羨ましく覚えば
【現】知らぬ道を羨ましく覚えば
【訳】知らない道を羨ましく思うなら
c
【古】角ある物の角を傾け
【現】角ある物が角を傾け
【訳】角がある動物がその角を突き出し
d
【古】牙ある物の牙を噛み出だす
【現】牙ある物が牙を噛み出だす
【訳】牙がある動物がその牙を剥き出しにする
また、もし品詞の区別がつくのでしたら「の」の前後に注目して、「名詞+の+名詞」なのか「名詞+の+動詞」なのかを見ると良いかと思います。ただし、「の」のすぐ後ろだけではなく、大きくざっくりと見ることがポイントです。
a:名詞(あらぬ道)+の+名詞(筵)
b:名詞(知らぬ道)+の+動詞(羨ましく覚えば)
c:名詞(角ある物)+の+動詞(角を傾け)
d:名詞(牙ある物)+の+動詞(牙を噛み出だす)
※一部、説明の分かりやすさを優先して、正しい語句を使用していない箇所があります。
シェアしよう!
そのほかの回答(1件)
名無しユーザー
この回答は削除されました。