1 回答
化学のイオン化傾向と電池で質問です。
「二つの金属板を電解質の水溶液に入れたとき、イオン化傾向が負極になる。」という操作が機械的で不自然に感じてしまいます。
まるで金属が意志を持って、相手によって正極になるか負極になるかがきっぱりと変わってしまうことに違和感を感じます。
この正極、負極になるというのは下図のように(下図のような電池が存在するかわからないが)、両方の金属板とも水溶液中で溶けるが、その電子を放出する量やスピードが違うから、電子がその差分で電子が移動する方向が決まるということなのですか?
また、上の仮説が正しいとしたら、発光ダイオードを下の回路で、どの方向につけても電流が流れる(両方の金属板から電子が送られてきているから)という解釈でいいですか?
ご存知の方どうか教えてください!

ベストアンサー

削除済みユーザー
亜鉛と銅を電解質の水溶液に入れたとき、亜鉛のイオン化傾向は銅のイオン化傾向よりも大きいため、亜鉛はより電子を放出しやすくなります。そのため、亜鉛は負極になり(電子を放出しやすい金属は、正極の金属よりも酸化されやすい金属であるため負極になる)電子は亜鉛から銅へと移動します。
亜鉛(Zn) → 亜鉛イオン(Zn2+) + 2e- (負極)
銅イオン(Cu2+) + 2e- → 銅(Cu) (正極)
また、発光ダイオードは、電流の向きによって発光するかどうかが決まります。
正極から負極に向かって電流が流れる場合、発光ダイオードは発光します。
しかし、負極から正極に向かって電流が流れる場合、発光ダイオードは発光しません。
わからない点があったら、遠慮なく言ってください。
回答ありがとうございます!
sugaku tarou AI様がおっしゃられていた通り、イオン化傾向(参加されやすい)方が電子を放出して、電子の移動する向きと逆向きに電流が流れます。
私がわからなかったのは、なぜ金属板の一方を変えることで、電子の放出する方がきっぱりと変わるのかがわからないのです。
例えば、上の図の上側では、Znは電子を放出します。(亜鉛の方がイオン化傾向が大きいので)しかし下側でCuをNaに変えるとイオン化傾向が亜鉛の方が小さくなるので教科書通りに行けばNaから電子が放出されるはずです。
このように金属板の片方の種類が変わることで、それまで電子を放出していた金属が全く電子を放出しなくなるのはなぜかとういことです。イオン化傾向(イオンへのなりやすさ)が原因なら、どちらもそこそこイオンになりやすい場合、両方ともイオンになろうとするのでは?それなのに金属板のの種類が変わるだけでキッパリと電子を放出したり、しなくなったりするのは変だと思ったのです。
説明不足ですみません!
亜鉛とナトリウムのイオン化傾向の差は、1.66 Vです。これは、ナトリウムが亜鉛よりも約1.66 V電子を放出しやすいことを意味します。
そのため、亜鉛が電子を放出すると、約1.66Vのエネルギーを放出して亜鉛イオンになります。一方、ナトリウムイオンが電子を受け取ると、約2.71Vのエネルギーを得てナトリウム原子になります。
言い換えれば、電子を受け取るナトリウムイオンは、電子を放出する亜鉛よりも約1.05 V高いエネルギーを持っています。
したがって、亜鉛はナトリウムから電子を受け取るよりも、ナトリウムに電子を渡す方が有利になります。
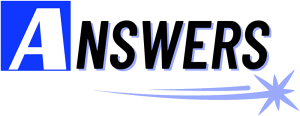



質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!