青線の部分はどうして言えるのでしょうか。
近似ということは慣れておらず、しかも大事だと思うのでしっかりと理解したいです。
お願いします。

ベストアンサー

削除済みユーザー
ある数の近似値は、その数をあらわす式中の微小項を に置き換えて得られる値を意味します。たとえば円周率の近似値としてよく が使われますが、これは円周率の真の値 において を微小とみなして に置き換えたものです。こうした置き換えからは当然誤差が生じるので、その誤差がどれほど大きいか、無視できる程度かの見積もりが一般には必要です。
において、 を に置き換えて得られる近似 からどの程度の誤差が生じるかを見積もってみます。 とおくと、
は区間 上で大きく増減し、 なら へ発散するけれども、 なら急速に へ近づくことが見てとれます。すなわち、
・ が に近いなら誤差ははなはだ大きく は近似として用をなさない
・ が に近いなら誤差は随分小さく は良い近似となる
ことが分かります。
化学を知らないのでよく分かりませんが、青線部は「酸が極めて弱いとき( が に近いとき)を除いて、 と近似しても誤差は小さく、近似が許される」と言っているように見えます。そういう意味だとしたら、その主張はたしかに妥当だと思います。
削除済みユーザー
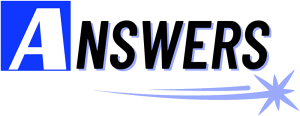



質問者からのお礼コメント
近似にこんなワケがあったのは初めて知りました!もっと勉強します💪